前回、『人の気持ちも自分の気持ちもわからない』というタイトルで記事を書きました。
あの時私は、「自分の気持ちがわからない」という夫の言葉が本当に不思議でした。
不思議で不思議で仕方ありませんでした。
他人の気持ちはわからなくても自分の気持ちはわかるよね?
「他人の気持ちがわからない」というなら理解できます。
他人の気持ちは難しい。
生まれ持った気質も育ってきた環境も違うから、他人の気持ちはなかなか理解できないものです。
でも。

自分の気持ちはわかるでしょう??
だって自分だから。
自分のことは自分が一番よくわかっているはず。
わかって当たり前でしょう。
そんな風に思ってて、夫が「自分の気持ちがわからない」と言った時には

なら私はあなたのこともっとわかんないよ!
と、じゃーどうしたらいいんだと混乱しました。
発達障害があると自分の気持ちや感情がわからない
でも、今は何となくわかります。
それは長男を通して気がつきました。
長男は、私が「学校どうだった?」と聞いても、「特に」とか「別に」としか答えません。
もう少し具体的に「クラブ楽しかったんじゃない?」と聞いたら「楽しかった」とは答えます。
でも、それだけ。
何が楽しかったのかは言わないので伝わってきません。
私は今まで長男の言葉で学校生活をイメージできたことがないんです。
長男が親に話したがらないタイプなのと、言葉で表現することが苦手な子だからだと思っていたけど、どうやら原因はそれだけじゃないみたい。
自分の気持ちがわからないんですね、きっと。
自分自身でわからない気持ちを他人に表現できるわけないか。
この気づきは私にとって、とても大きなものでした。
精神科で気持ちを代弁してあげてと言われる
そういえば、長男の精神科でこんなこと言われました。
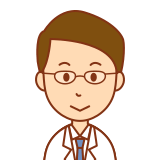
長男君の気持ちを代弁してあげてください
長男がゲームで負けてイライラしてたら「悔しかったね」
大好きなお菓子貰えた時に「嬉しいね」
そうやって、声を掛けてあげてくださいと言われたことがありました。
正直、やってたんですけどね。
保育士してたんですが、こういうの保育の基本なんですよ。
だから身についていて自然にやってたことなんだけど。
自分の気持ちに気づきにくい長男にはそれでも足りないのかもしれません。
先生は、私が彼の気持ちを代弁することで長男が自分の気持ちに気づけるようにしたかったのだと思います。
でもコレ、難しいですよね。
代弁するということは、相手の気持ちがわからないと無理だから。
2歳3歳のちびっ子相手の保育現場とは違うから。
成長した長男には複雑な感情も芽生えているし、難しいことだと思います。
でも彼の役に立つのなら、日ごろから長男の様子見て、なるべくやっていこうかな。
子どもの頃からの療育が大事
ただコレ、相手が夫となると完全に無理だと思う。
夫は自分の気持ちがわからず主治医に言われた宿題ができなかったけど。
ここで私が夫に言うの?
「仕事行きたくなかったね」
「お酒美味しいね~」
…って、ムリムリムリムリ!
無理でしょ。できないわ、こんなん。夫だって嫌でしょう。
考えてみたら、夫は両親に気持ちの代弁はしてもらってきたのだろうか。
義家族のことを思い浮かべてみると…
ないな…って思う。うんうん、多分無いと思う。
言葉数は多いんですけどね。
お義父さんもお義母さんもよくしゃべる人で、食卓を囲んで家族でおしゃべりする場面は多く見てきたけど。
言葉が一方通行なんですよ。
みんなが自分のことだけしゃべる感じ。
相手の気持ちに(そうなんだー楽しかったね)みたいな共感や代弁がない。
決して嫌な空気ではないんです。楽しく会話はしてるんだけど、それぞれ自分のことを話す感じで、そこに気持ちの交流はあまりないように思います。
そんな感じ。
義家族もみんな特性持ってますからね。
夫も療育に通えたらよかったのにな。
やはり子どもの頃からの療育は大事だと、改めて感じたのでした…。


コメント